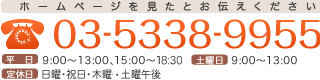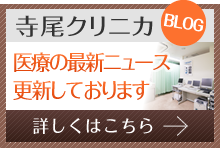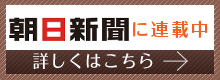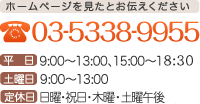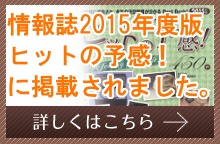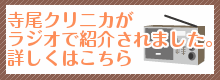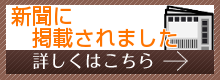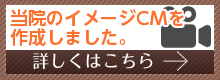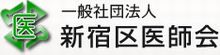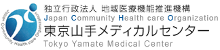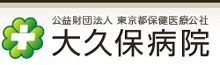寺尾クリニカブログ
2026年1月20日 火曜日
禁煙外来を開始しました
昨年から、禁煙外来を開始しました
1) 57ppmと3ppm。数値が語る「体の真実」
今日、私の外来に来られた患者さんの呼気一酸化炭素(CO)濃度は57ppm(非喫煙者の場合10ppm以下)でした。全身の細胞が深刻な「酸欠」に喘いでいる状態です。 実は、非喫煙者である私の場合3ppmでした。
57ppmという数字がいかに異常で、体が悲鳴を上げているかは一目瞭然です。
一方で、最近女性に多い「加熱式タバコ」のユーザーは、測定しても2〜4ppmと、私のような非喫煙者と変わらない数値が出ます。今日の患者さんも「加熱式のほうが安全だと思っていた」とおっしゃっていましたが、ここに大きな罠があります。
2) 加熱式タバコに潜む「美容と健康の罠」
加熱式タバコは一酸化炭素こそ少ないですが、血管を強力に収縮させる「ニコチン」の摂取量は紙巻きタバコと変わりません。
見た目への影響:ニコチンは血流を阻害し、肌のターンオーバーを遅らせ、大切なコラーゲンを破壊します。
依存の深さ:数値が低いため「自分は大丈夫」と錯覚し、禁煙の決断を遅らせてしまいます。
美容や清潔感のために加熱式を選んでいるのであれば、それは本末転倒です。本当の美しさを取り戻すには、脳と血管をニコチンから解放しなければなりません。
3) 根性ではなく「科学」でやめる
禁煙が続かないのは意志が弱いからではなく、脳の報酬系がニコチンに支配されているからです。当院では、飲み薬の**バレニクリン(チャンピックス)**を用いた治療を行っています。
離脱症状を和らげる(アゴニスト効果):脳内の受容体に作用して少量のドーパミンを出し、禁煙時のイライラを抑えます。
満足感をブロックする(拮抗作用):ニコチンが受容体に結びつくのを防ぎ、万が一吸ってしまっても「美味しくない」と感じさせます。
最新の解析データでは、この薬を用いることで、自力(プラセボ)での禁煙に比べて成功率が約2.3倍に高まることが証明されています。
4)「頑張りすぎない」ための対面サポート
「副作用が怖い」という方もいらっしゃいますが、医学的に対処可能です。(約29.4%)ですが、当院では適切な吐き気止めを処方し、対面での診察を通じてきめ細かくサポートします。
この吐き気も、多くの方は7日間ほどで体が慣れてきます。 最初の1週間を医学の力で乗り越えれば、その先には「吸いたいと思わない」快適な生活が待っています。
実際に当院では、最近4人の方が治療を始められましたが、早い方では2〜3週間で「もう吸いたいと思わなくなった」と、驚くほど晴れやかな顔で話してくれます。
最後に
禁煙は、自分を責める苦行ではありません。医学という確立されたツールを使いこなし、自分の人生の主導権を取り戻す。それこそが本当の「自律」です。
呼気CO濃度を非喫煙者レベルに保ち、血管を解放して、見た目年齢を最大13歳若返らせる。そのために必要なのは、根性ではなく、外来のドアを叩くという合理的な選択だけです。
1) 57ppmと3ppm。数値が語る「体の真実」
今日、私の外来に来られた患者さんの呼気一酸化炭素(CO)濃度は57ppm(非喫煙者の場合10ppm以下)でした。全身の細胞が深刻な「酸欠」に喘いでいる状態です。 実は、非喫煙者である私の場合3ppmでした。
57ppmという数字がいかに異常で、体が悲鳴を上げているかは一目瞭然です。
一方で、最近女性に多い「加熱式タバコ」のユーザーは、測定しても2〜4ppmと、私のような非喫煙者と変わらない数値が出ます。今日の患者さんも「加熱式のほうが安全だと思っていた」とおっしゃっていましたが、ここに大きな罠があります。
2) 加熱式タバコに潜む「美容と健康の罠」
加熱式タバコは一酸化炭素こそ少ないですが、血管を強力に収縮させる「ニコチン」の摂取量は紙巻きタバコと変わりません。
見た目への影響:ニコチンは血流を阻害し、肌のターンオーバーを遅らせ、大切なコラーゲンを破壊します。
依存の深さ:数値が低いため「自分は大丈夫」と錯覚し、禁煙の決断を遅らせてしまいます。
美容や清潔感のために加熱式を選んでいるのであれば、それは本末転倒です。本当の美しさを取り戻すには、脳と血管をニコチンから解放しなければなりません。
3) 根性ではなく「科学」でやめる
禁煙が続かないのは意志が弱いからではなく、脳の報酬系がニコチンに支配されているからです。当院では、飲み薬の**バレニクリン(チャンピックス)**を用いた治療を行っています。
離脱症状を和らげる(アゴニスト効果):脳内の受容体に作用して少量のドーパミンを出し、禁煙時のイライラを抑えます。
満足感をブロックする(拮抗作用):ニコチンが受容体に結びつくのを防ぎ、万が一吸ってしまっても「美味しくない」と感じさせます。
最新の解析データでは、この薬を用いることで、自力(プラセボ)での禁煙に比べて成功率が約2.3倍に高まることが証明されています。
4)「頑張りすぎない」ための対面サポート
「副作用が怖い」という方もいらっしゃいますが、医学的に対処可能です。(約29.4%)ですが、当院では適切な吐き気止めを処方し、対面での診察を通じてきめ細かくサポートします。
この吐き気も、多くの方は7日間ほどで体が慣れてきます。 最初の1週間を医学の力で乗り越えれば、その先には「吸いたいと思わない」快適な生活が待っています。
実際に当院では、最近4人の方が治療を始められましたが、早い方では2〜3週間で「もう吸いたいと思わなくなった」と、驚くほど晴れやかな顔で話してくれます。
最後に
禁煙は、自分を責める苦行ではありません。医学という確立されたツールを使いこなし、自分の人生の主導権を取り戻す。それこそが本当の「自律」です。
呼気CO濃度を非喫煙者レベルに保ち、血管を解放して、見た目年齢を最大13歳若返らせる。そのために必要なのは、根性ではなく、外来のドアを叩くという合理的な選択だけです。
投稿者 寺尾クリニカ | 記事URL
2026年1月15日 木曜日
2026年6月、 1100品目の薬が「実質自費」になりますので注意してください
日本の医療制度において、これまでにない大きな変化が2026年6月から本格施行されます。
これまで「病院に行けば安く手に入る」と信じられてきた身近な薬、約1100品目が、実質的な自己負担増(選定療養)の対象になります。
国は「市販品と同じような薬は、自分でお金を払いなさい」という明確なメッセージを出し始めました。
1)家庭を直撃する、具体的な薬名
対象となるのは、多くの日本人が日常的に、そして「とりあえず」と希望してきた薬ばかりです。
花粉症・鼻炎: アレグラなどの抗アレルギー薬、点鼻薬
痛み・肩こり: ロキソニン、湿布薬全般
風邪:カルボシステイン(去痰剤)
お腹の悩み: 酸化マグネシウム(便秘薬)、整腸剤、胃薬
日常のトラブル: 口内炎の薬、おでき、皮膚の痒み止め、水虫の薬
これまでは「診察料+数百円」で済んでいたものが、6月からは「特別の料金」として薬剤費の25%程度が上乗せされ、窓口での支払額が跳ね上がります。
2) 「コンビニ受診」の代償
なぜ、このような過酷な制度が始まるのか。それは、多くの国民が健康を「国や医者任せ」にしてきたツケでもあります。
「ちょっと鼻水が出るから」「予備の湿布が欲しいから」と、安易に使い続けてきた結果、制度が維持できなくなったのです。
6月以降、こうした「コンビニ感覚」での受診は、家計をダイレクトに圧迫するコストとなります。
3)医療機関も、患者も、淘汰されるとおもいます
この改定により、単に「患者が欲しがる薬を出すだけ」の医療機関は、負担増を嫌う患者に選ばれなくなり、大幅な減収に見舞われるでしょう。
そして患者側も淘汰されます。気づかぬうちに高額な医療費を払い続け、家計を破綻させる。そんな「無知のコスト」を払わされる層が大量に現れます。
4)次のことをやってください
「その薬、本当に必要か?」を問い直す: 生活習慣(食事・睡眠・運動)で改善できることに、安易に薬を使わない覚悟を持つこと。
6月までに、自分の使っている薬が対象かどうか、調べましょう。
自分の身体を他人任せにしない。
病気にならない身体作りこそが、最大の防衛策です。
先発品から後発品に変えること。
これまで「病院に行けば安く手に入る」と信じられてきた身近な薬、約1100品目が、実質的な自己負担増(選定療養)の対象になります。
国は「市販品と同じような薬は、自分でお金を払いなさい」という明確なメッセージを出し始めました。
1)家庭を直撃する、具体的な薬名
対象となるのは、多くの日本人が日常的に、そして「とりあえず」と希望してきた薬ばかりです。
花粉症・鼻炎: アレグラなどの抗アレルギー薬、点鼻薬
痛み・肩こり: ロキソニン、湿布薬全般
風邪:カルボシステイン(去痰剤)
お腹の悩み: 酸化マグネシウム(便秘薬)、整腸剤、胃薬
日常のトラブル: 口内炎の薬、おでき、皮膚の痒み止め、水虫の薬
これまでは「診察料+数百円」で済んでいたものが、6月からは「特別の料金」として薬剤費の25%程度が上乗せされ、窓口での支払額が跳ね上がります。
2) 「コンビニ受診」の代償
なぜ、このような過酷な制度が始まるのか。それは、多くの国民が健康を「国や医者任せ」にしてきたツケでもあります。
「ちょっと鼻水が出るから」「予備の湿布が欲しいから」と、安易に使い続けてきた結果、制度が維持できなくなったのです。
6月以降、こうした「コンビニ感覚」での受診は、家計をダイレクトに圧迫するコストとなります。
3)医療機関も、患者も、淘汰されるとおもいます
この改定により、単に「患者が欲しがる薬を出すだけ」の医療機関は、負担増を嫌う患者に選ばれなくなり、大幅な減収に見舞われるでしょう。
そして患者側も淘汰されます。気づかぬうちに高額な医療費を払い続け、家計を破綻させる。そんな「無知のコスト」を払わされる層が大量に現れます。
4)次のことをやってください
「その薬、本当に必要か?」を問い直す: 生活習慣(食事・睡眠・運動)で改善できることに、安易に薬を使わない覚悟を持つこと。
6月までに、自分の使っている薬が対象かどうか、調べましょう。
自分の身体を他人任せにしない。
病気にならない身体作りこそが、最大の防衛策です。
先発品から後発品に変えること。
投稿者 寺尾クリニカ | 記事URL
2026年1月 8日 木曜日
加工食品毎日摂取すると寿命を短縮します
【加工食品大国ドイツの教訓】
私たちは、欧米の食文化を便利さゆえに取り入れてきました。しかし、その代償はあまりに大きいものです。
加工肉(ソーセージやハムやベーコンなど)の本場であるドイツでは、大腸がんの罹患率が非常に高いことが知られています。
WHOも「毎日50gの加工肉がリスクを18%高める」と警告していますが、このドイツの現状こそが、加工食品に頼りすぎることの危険性を証明しているのです。
【他人事ではない、日本の食文化の危機】
今、日本全体で大腸がんが増えているのは、決して偶然ではありません。
便利な加工食品に依存し、日本人が本来持っていた「腸を守る力」を失っているからです。
日本ではエネルギーの約40%を加工食品です。加工肉以外にも人工甘味料、揚げ物・スナック菓子です。欧米に比べると少ないですが、これでは癌だけでなく脳梗塞や心筋梗塞などの病気が起きても不思議ではありません。
【今日から選び直すべき「命を繋ぐ食材」】
知識がないことは、自分の健康をギャンブルにかけるのと同じです。調べる時間がない方のために、具体的に何を食べるべきかを示します。
• 「魚」と「大豆(納豆)」を主役に: 肉(特に加工肉)を減らし、魚や納豆を積極的に選んでください。納豆などの発酵食品は、腸内の毒素を産生する菌を抑え込み、腸内環境を根本から整えます。
• 「具沢山の味噌汁」で塩分を追い出す: 汁を飲むのではなく、野菜や海藻を「食べる」ための味噌汁に。食物繊維が腸を掃除し、野菜のカリウムが過剰な塩分を排出します。
• 加工度の低い食材を選ぶ: 原形がわからない加工品ではなく、命の形がそのまま見える食材を選び、自炊の機会を増やしましょう。
• 揚げ物は食べないようにする:ポテトチップス、フライドポテトはさけてください。
• 人工甘味料を含む飲料水は飲まない:腸内細菌のバランスを壊し、体重が増えます。
【結び】 人生は1回きりです。加工食品ではなく、日本食を食べて健康になりましょう。癌、生活習慣病の予防になりますよ。
私たちは、欧米の食文化を便利さゆえに取り入れてきました。しかし、その代償はあまりに大きいものです。
加工肉(ソーセージやハムやベーコンなど)の本場であるドイツでは、大腸がんの罹患率が非常に高いことが知られています。
WHOも「毎日50gの加工肉がリスクを18%高める」と警告していますが、このドイツの現状こそが、加工食品に頼りすぎることの危険性を証明しているのです。
【他人事ではない、日本の食文化の危機】
今、日本全体で大腸がんが増えているのは、決して偶然ではありません。
便利な加工食品に依存し、日本人が本来持っていた「腸を守る力」を失っているからです。
日本ではエネルギーの約40%を加工食品です。加工肉以外にも人工甘味料、揚げ物・スナック菓子です。欧米に比べると少ないですが、これでは癌だけでなく脳梗塞や心筋梗塞などの病気が起きても不思議ではありません。
【今日から選び直すべき「命を繋ぐ食材」】
知識がないことは、自分の健康をギャンブルにかけるのと同じです。調べる時間がない方のために、具体的に何を食べるべきかを示します。
• 「魚」と「大豆(納豆)」を主役に: 肉(特に加工肉)を減らし、魚や納豆を積極的に選んでください。納豆などの発酵食品は、腸内の毒素を産生する菌を抑え込み、腸内環境を根本から整えます。
• 「具沢山の味噌汁」で塩分を追い出す: 汁を飲むのではなく、野菜や海藻を「食べる」ための味噌汁に。食物繊維が腸を掃除し、野菜のカリウムが過剰な塩分を排出します。
• 加工度の低い食材を選ぶ: 原形がわからない加工品ではなく、命の形がそのまま見える食材を選び、自炊の機会を増やしましょう。
• 揚げ物は食べないようにする:ポテトチップス、フライドポテトはさけてください。
• 人工甘味料を含む飲料水は飲まない:腸内細菌のバランスを壊し、体重が増えます。
【結び】 人生は1回きりです。加工食品ではなく、日本食を食べて健康になりましょう。癌、生活習慣病の予防になりますよ。
投稿者 寺尾クリニカ | 記事URL
2025年12月29日 月曜日
年末年始の診療について
今年もあとわずかですね
年末年始の診察について
12月31日から1月4日まで休診とさせていただきます。
本日も、インフルエンザの患者さんが来院しました。
これからはコロナ感染の増えるとおもいますので、
十分体調管理にはきおつけてください。
よいお年をお迎えください。
寺尾クリニカ 寺尾一郎
年末年始の診察について
12月31日から1月4日まで休診とさせていただきます。
本日も、インフルエンザの患者さんが来院しました。
これからはコロナ感染の増えるとおもいますので、
十分体調管理にはきおつけてください。
よいお年をお迎えください。
寺尾クリニカ 寺尾一郎
投稿者 寺尾クリニカ | 記事URL
2025年12月21日 日曜日
生存率を変える膵臓がん「5つの意外な前兆」と見落としがちなリスク
先日、私の患者さんがすい臓がんになりました。
私はこの患者さんを心臓病と高血圧症で治療していました。
糖尿病に関しては、近くの国立病院で専門医が治療していました。
私も心配であり、血液検査で血糖とHbA1cを経時的に観察していました。
今年になりこの値が治療しているにも関わらず、悪化しているので、国立病院の医師に連絡したところ直ぐ入院になりました。
2日前に患者さんから電話があり、すい臓がんが見つかり今月に手術をすることになりました。
私は、驚きと怒りを感じました。
専門医でありながら病状が悪化しているのに放置している許せなかったです。もっと早く対応してほしかったです。
そこで、すい臓がんについて皆さんにわかってもらいたくブログに書きました。
「見つかった時には手遅れ」。 そんな絶望的なイメージが強い膵臓がんですが、「意外なサイン」を発信していることが近年の研究で分かってきました。
「サイレントキラー」の正体を見破り、早期発見のチャンスを逃さないための5つ事をお伝えします。
1. 「糖尿病」は原因ではなく、がんの"結果"かもしれない
通常、糖尿病はがんのリスク因子と言われますが、実は逆のパターンがあります。膵臓がんそのものが糖尿病を引き起こすケースです。 これは腫瘍が膵臓を物理的に傷つけることで発症します。
2. 50歳を過ぎての「突然の糖尿病」は最大の警告
もし50歳を過ぎてから、家族歴も肥満もないのに突然糖尿病と診断されたら注意が必要です。 50歳以上の新規発症者は、3年以内に膵臓がんと診断されるリスクが6〜8倍に跳ね上がります。
3. リスクは「足し算」ではなく「掛け算」で増える
日本膵臓学会のガイドラインが示すリスクの数値は衝撃的です。
喫煙: 2〜3倍
糖尿病:2倍
過度の飲酒:3倍
慢性膵炎: 4〜8倍
家族歴: 13倍
遺伝性膵炎: 53倍
これらが重なっている場合、リスクは指数関数的に高まります。
4. 「20歳の時の体型」が数十年後のリスクを決める
驚くべきことに、若年期の健康状態が将来に影を落とします。日本の研究では、20歳時点で肥満(BMI30以上)だった男性は、将来の膵臓がんリスクが3.5倍になることが判明しました。がんは、私たちが思うよりもずっと前から準備を始めているのかもしれません。
5. 「血液検査の結果が正常」でも安心できないワケ
よく使われる腫瘍マーカー(CA19-9)ですが、実は早期発見には不向きです。
良性の病気でも数値が上がる。
日本人の約5%は、遺伝的にこの数値が上がらない。 ある調査では、膵臓がんが見つかった患者の全員が「検査値は正常」だった例もあります。
数値だけに頼らず、複数の症状や変化を総合的に見ることが不可欠です。
まとめ:その「違和感」を放置しないでください。
膵臓がんは、決して「無症状」ではありません。
「50歳を過ぎての血糖値上昇」「急激な体重減少」「背中の違和感」。 これらが重なったとき、医学の進化により、高リスク群を特定する精度は確実に上がっています。
まずは「知ること」から、自分の体への向き合い方を変えてみませんか?
私はこの患者さんを心臓病と高血圧症で治療していました。
糖尿病に関しては、近くの国立病院で専門医が治療していました。
私も心配であり、血液検査で血糖とHbA1cを経時的に観察していました。
今年になりこの値が治療しているにも関わらず、悪化しているので、国立病院の医師に連絡したところ直ぐ入院になりました。
2日前に患者さんから電話があり、すい臓がんが見つかり今月に手術をすることになりました。
私は、驚きと怒りを感じました。
専門医でありながら病状が悪化しているのに放置している許せなかったです。もっと早く対応してほしかったです。
そこで、すい臓がんについて皆さんにわかってもらいたくブログに書きました。
「見つかった時には手遅れ」。 そんな絶望的なイメージが強い膵臓がんですが、「意外なサイン」を発信していることが近年の研究で分かってきました。
「サイレントキラー」の正体を見破り、早期発見のチャンスを逃さないための5つ事をお伝えします。
1. 「糖尿病」は原因ではなく、がんの"結果"かもしれない
通常、糖尿病はがんのリスク因子と言われますが、実は逆のパターンがあります。膵臓がんそのものが糖尿病を引き起こすケースです。 これは腫瘍が膵臓を物理的に傷つけることで発症します。
2. 50歳を過ぎての「突然の糖尿病」は最大の警告
もし50歳を過ぎてから、家族歴も肥満もないのに突然糖尿病と診断されたら注意が必要です。 50歳以上の新規発症者は、3年以内に膵臓がんと診断されるリスクが6〜8倍に跳ね上がります。
3. リスクは「足し算」ではなく「掛け算」で増える
日本膵臓学会のガイドラインが示すリスクの数値は衝撃的です。
喫煙: 2〜3倍
糖尿病:2倍
過度の飲酒:3倍
慢性膵炎: 4〜8倍
家族歴: 13倍
遺伝性膵炎: 53倍
これらが重なっている場合、リスクは指数関数的に高まります。
4. 「20歳の時の体型」が数十年後のリスクを決める
驚くべきことに、若年期の健康状態が将来に影を落とします。日本の研究では、20歳時点で肥満(BMI30以上)だった男性は、将来の膵臓がんリスクが3.5倍になることが判明しました。がんは、私たちが思うよりもずっと前から準備を始めているのかもしれません。
5. 「血液検査の結果が正常」でも安心できないワケ
よく使われる腫瘍マーカー(CA19-9)ですが、実は早期発見には不向きです。
良性の病気でも数値が上がる。
日本人の約5%は、遺伝的にこの数値が上がらない。 ある調査では、膵臓がんが見つかった患者の全員が「検査値は正常」だった例もあります。
数値だけに頼らず、複数の症状や変化を総合的に見ることが不可欠です。
まとめ:その「違和感」を放置しないでください。
膵臓がんは、決して「無症状」ではありません。
「50歳を過ぎての血糖値上昇」「急激な体重減少」「背中の違和感」。 これらが重なったとき、医学の進化により、高リスク群を特定する精度は確実に上がっています。
まずは「知ること」から、自分の体への向き合い方を変えてみませんか?
投稿者 寺尾クリニカ | 記事URL